出来事
本年もよろしくお願いいたします
磐崎中学校の保護者のみなさま、そして地域のみなさま、本年も何卒よろしくおねがいいたします。
校地内の巡視に来てみましたところ、今朝も湯長谷の丘には素晴らしい朝日が上がってきました。
やはり、初日の出というものは、とても感慨深く思えてしまいます。
この初日の出に、磐崎中学校の子どもたちの健康と活躍をお祈りさせていただきました。
本年においても、子どもたち一人一人が、今朝の太陽のように光を放ちながら力強く邁進していけるよう、精一杯の支援をしてまいります。

よいお年をお迎えください
今年1年間、磐崎中の保護者のみなさまや地域の方々には、本校の教育活動を進めていく上で、多大なるご理解とご協力をいただきました。改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。
明日からは年末休暇に入り、1月3日までの6日間は空直日となります。ご理解をいただければ幸いです。
さて、3年生のみなさん。
夢を叶えるための準備は、計画通りに進んでいるでしょうか。
学校では、みなさんの受け入れ態勢を万全にして、お正月を迎えようとしています。
勝負の1月4日(木)まで、残すところちょうど一週間となりました。
頑張れることは、まだまだたくさん残されているはずです。
そして、君たちは、もっともっと頑張れるはずです。
頑張れ、頑張れ、3年生。

金づちの音 ニスの匂い
丁寧に作業を進めてきたためか、技術の授業で完成までたどり着けなかった子どもたちが、黙々と最後の仕上げをしていました。
今日ですべての生徒が完成に漕ぎ着けたようです。
いよいよ今年の部活動も、明日で最後となります。
今朝は、突然の雪雲が校庭をうっすらと白く染めて、何事もなかったかのように去っていってしまいました。
寒い、寒い一日でした。


いつもお洗濯、ありがとうございます
氷点下まで気温が下がり、地中に含まれている水分が凍ってカチカチになってしまった校庭は、今度は太陽に照らされ気温が上がると、その水分が徐々に溶け出してしまい、カチカチからドロドロへと変貌してしまいます。
そのため、野球部、サッカー部、ソフトボール部、陸上部のみなさんのシューズやジャージは、残念ながら泥だらけになってしまいます。
お子さんたちが、泥だらけになって自宅に戻っているかと思いますが、いつもいつもお洗濯、本当にありがとうございます。
しかし、子ども達はそんな親御さんのご苦労を知ってか知らずか、足元を泥だらけにして今日も笑顔で校庭を走り回っていました。
今年も残すところ、あと5日間です。

ちょっとした気分を
本日はクリスマスです。
しかし、クリスマスであることを忘れさせてくれるくらい、どの部活動も朝から熱心に活動しています。
校庭でも、体育館でも、武道場でも、音楽室でも、美術室でも...
ただ、さくら学級だけは違いました。
誰もいない教室に、ツリーがひっそりと立っています。
ちょっとしたクリスマス気分を味わうことができました。
Happy Holidays!

ふたりでひとつ
ダブルスの練習なのでしょう。
何度も何度もポジショニングを入れ替えながら、集中して返球していました。
互いに呼吸を合わせながら、一つのポイントを取りにいく。
そこにダブルスの魅力があるように感じます。
真剣さの中にある笑顔が、きらりと光っていました。
明日の大会でも、その笑顔が光ることを願っております。

保護者のみなさまのご支援、よろしくお願いいたします。
冬至は一年の中でお昼の時間帯が一番短い日とされているため、知識のない私は、日の出の時間帯も一年の中で一番遅いだろうと勝手に思い込み、シャッターを切ってしまいました。
ところがです。
日の出はこれからも少しずつ遅くなっていくそうです。
また一つ勉強になりました。
さて、本日、無事に終業式を終えることができました。
明日から始まる17日間の冬休み。
常磐地区では、インフルエンザの罹患者が少しずつ増えてきているようです。
病気にかからず、充実した長期休業になりますよう、ご家庭でのご支援を何卒よろしくお願いいたします。

保護者のみなさま、ありがとうございました。
2学期におきましても、大過なく教育活動を進めてくることができましたのも、保護者のみなさまのご理解、ご協力があってのこそです。ありがとうございました。
本日、お子さんにも配付させていただきましたが、学校だより「やかた」をアップさせていただきます。
ご一読いただければ幸甚です。
やかた5.pdf
食べるチカラ
「食べる力」は「生きる力」とも言われ、食育の充実が叫ばれています。
給食センターの職員のみなさんのご尽力のもと、栄養のバランスはもちろんのこと、学校給食そのものを生きた教材として、地場産物や日本古来の食文化の理解などにもつながるように創意工夫を凝らしたメニューとなっております。
3年生のみなさんは、あと何回、この学校給食を食することができるのでしょう。
本日が今年最後の給食でした。
おいしい給食とも、約3週間ほどのお別れです。
そして、いよいよ明日は、2学期終業式を迎えます。

感謝のカタチ
「生徒が職員室を掃除しなければならないのは、なぜですか」という新聞記事を目にしました。
「自分たちが使っていない場所を、なぜ僕たちが清掃しなければならないんだ」と疑問を抱くこと。
生徒の立場からすれば、まさしく正論です。
もしかしたら、このことの議論は尽きないのかもしれません。
しかし、磐崎中では一つの事実が存在しています。
それは、職員室の清掃に来てくれている生徒のみなさん全員が、膝を付いて床の隅々まで熱心に雑巾をかけてくれること。
この事実を「当たり前」と捉えるのではなく、子どもたちへの「感謝の念」を抱くこと。
その感謝の気持ちを我々教員が抱いていれば、子どもたちが抱いているかもしれない疑問も…
その新聞記事を読んだとき、そんな風に感じました。
しっとりとした授業をめざしたい
筆を入れるときの緊張感
墨汁の匂い
静寂に包まれた教室
現在、国語科では全学年共通で、書写の授業を展開しています。
どんなに技術革新が進もうが、どんなに社会文化が変わろうが、やはり不易というものを大切にしたいと思います。
伝統的な文字文化に触れ、そしてその文化に親しむ態度を育むことを通して、本学期の国語科の学びを終えることができればと考えております。
17日間をどう闘う
本日、月曜日を無事に終えることができましたので、あと4日間が過ぎれば冬休みです。
3年生にとりましては、高校受験に向けて、まとまった時間が取れる最後のチャンスとなります。
今年度予定されている冬休みは、17日間。
ぜひ行き当たりばったりの17日間にするのではなく、見通しを持った17日間にしたいものです。
そのためにも、計画を練ることは重要になるはずです。
もし可能であれば、クリスマスは家族とともに一緒に過ごす時間を設けてみてください。
大晦日くらいは、ゆっくりとテレビでも観ながら、年を越す瞬間を味わってください。
ぜひ、元旦くらいは、家族と祝い、新年の抱負をじっくりと語り合ってください。
だからこそ、計画を立てることが重要になってくるはずなのです。
それも、実施可能な計画を。
冬休みは、ある程度の余裕をもたせた綿密な計画を立てること。
そのことが命運を握っているのではないか、そう思います。
本日は、今年最後の3年生の学年集会が実施されました。
当然のことですが、集会の中身は受験一色でした。

頑張れ、頑張れ!
バスケットコートを縦横無尽に走ります。
水の入ったペットボトルを両手に握り締め、ディフェンスの練習をしていました。
いつまでもいつまでも、根気強く、ディフェンスの練習を続けていました。
「ファイトー!」の声が、体育館に響いていました。
頑張れ、頑張れ、バスケ部。


精一杯の想いを伝える
各学年の代表者1名ずつが、2学期の反省と新学期の抱負について作文を披露してくれましたが、今日は4人目として、さくら学級からも一人、発表してくれた生徒がいました。
「大丈夫かなぁ、緊張していないかなぁ」と心配していましたが、400人もいる大勢の前で、読み間違えることもなくしっかりと発表することができました。
たぶん、時間をかけて作文を推敲し、何度も何度も読む練習を繰り返してきたのでしょう。
心がじんわりと熱くなりました。
もちろん、各学年を代表して発表してくれた3名のみなさんの発表も、的確に自分の課題を捉え、次につなげていこうとする想いが伝わる素晴らしい発表でした。
全校集会が終わった後、さくら学級に足を運びましたら、ほっとした表情で、級友のみんなと一緒に、柔らかな音色のハンドベルを鳴らしていました。
曲名は「ジングルベル」。
もうすぐそこまで、クリスマスはやってきています。

日本一になる答えを見つける
3年生の旧キャプテンから檄が飛びます。
いよいよ今週末、「ベースボールクラシック2017」全国大会が東京で開催されます。
磐崎中野球部は、福島県大会を勝ち抜き、県代表チームとして出場してきます。
数メートルの短い距離の中で、制限時間内にどれだけのキャッチボールの回数を刻めるのか。
2分間の試技が終わったら、すぐに輪になって意見を出し合います。
そこには「やらされている部活」からはかけ離れた世界がありました。
最高のパフォーマンスをするためにはどうすればよいのか、自分たちでその答えを見つけ出そうとしています。
そして、今回は裏方にまわっている2年生の現キャプテンは、誰よりも声を張り上げ、先輩を含めた選手のみんなを鼓舞しています。
とてもとても寒い中での練習でしたが、いつまでも見ていたいと思うような清々しい練習風景でした。


あたたかいことば
この時期に行われる学年集会は、2学期を振り返っての反省、さらには冬休み中における学習への取り組みや安全指導が中心となりますが、2年生のみなさんは、学年主任の先生から、厳しくも温かい言葉をいただいていました。
「指示だけを待つような人間にはならない。他人任せの人にはなってはいけない。」
「自分から先に気付けること。自分から問題提起をし、具体的な提案をしてみること。そして、自分から実践に移してみること。」
まさしくその力が、これからの社会を生き抜くために必要な資質・能力の一つであるはずです。
後は、その言葉をどう受け止め、どう生かしていくのか。
ピンと張り詰めた空気の中、西に沈みかけようとしている太陽の光が、学年主任の先生の言葉と同じように、みなさんに温かく降り注いでいました。

学び続ける存在でありたい
しかし、今では、それではもう立ち行かなくなると言われています。
それは、なぜか。
それには、AIの存在があるからです。
残念ながら、我々の能力では、必要な情報を暗記する量においても、計算処理能力の速さにおいても、AIには全く歯が立ちません。
そのため、今存在する多くの職業がAIに奪われていくと言われています。
それでは、そのような状況を考えたとき、今の子どもたちにどのような力を付けていかなければならないのか...
付けるべき力が変わってきたのであれば、当然、その力を付けるための授業も変わらなければなりません。
本日は、2年生の教室で研究授業が行われました。
目の前にいる子どもたちと同様、我々も学び続ける存在でありたいと思います。


「なりたい自分」を見付ける
昼休みには、どの教室でも自分の机に向かって、黙々と学習に励んでいる姿を目にすることができました。
2年生にとっては、来年度の受験に向けて、ある程度の指標となるテストになることと思います。
現在の学力がどの程度なのか、客観的に捉える機会となるはずです。
「受験まであと1年もある」と考えるのか、「受験まであと1年しかない」と考えるのか。
その捉え方一つで、今後の取り組み方も変わってくるはずです。
しかし、それよりも、まずは「将来の夢」を持ってほしい。「なりたい自分」を見付けてほしい。
そう願います。
すべては、そこから始まるような気がします。
黙々と学習に励んでいる、みなさんのその横で、ウイルスからみなさんを守るかのように、加湿器がモクモクと水蒸気を出し続けていました。

次へとつなげる2週間
白く映る息を弾ませながら、元気よくグラウンドへと駆け出していきました。
本当に楽しそうにプレーをします。
彼らの表情から、それがありありと伝わってきます。
さぁ、2学期も残り2週間。
この2週間が、子どもたちにとって2学期の“消化試合”とならないよう、一日一日に明確な目標を持った上での充実した2週間にさせていきたいものです。
サッカー部のみなさんは、みんなで呼吸を合わせ、マサイ族のように垂直にジャンプをしていました。
本当に楽しそうにプレーをします。


命を守る 自分で守る
だからこそ、本校の登下校における交通指導には、念には念を入れなければなりません。
本日は、いわき中央署からお巡りさんを講師としてお招きし、交通教室を実施しました。
子どもたちの登下校の様子を基に、どのようなところに危険が潜んでいるのか、具体的に学ぶ機会を設けました。
まずは、安全に登下校ができること。
子どもたちの命を守るための大切な時間であると考えています。
背筋を伸ばし、真剣な眼差しで、お巡りさんの講話を聞いている3年生の姿、誇らしく思えてきます。

学ぶということ
中学生時代、なぜだかとても不思議な感覚でしたが、フラスコに入っている水をガスバーナーで沸騰させるだけでも、ワクワクしたことを覚えています。
たぶん、そこには「学びの原点」があったからでしょう。
今日の理科の授業でも、ワクワク感満載の子どもたちの表情がそこにありました。
やはり、我々が求めるべき授業は、「わかって、できて、おもしろい」授業のはずです。
子どもたちの見つめる視線の先では、どんな実験が繰り広げられているのか、ふと覗いてみたくなりました。

ボクが目になる
とてもかわいい存在でした。
でも、「かわいい」というだけでは終われない現実も、そこにはあるのだろうなと感じました。
1年生の総合的な学習の時間では、福祉をテーマにして学びを続けていますが、本日はその一環として、盲導犬講座が行われました。
実際に目が見えないことの疑似体験を通して、多くの気付きに出会えたはずです。
福島県内を見渡しても、盲導犬の数は20頭に満たないのが現状のようです。
そう考えたとき、何かできることはないのだろうか。
今日の学びが、次の何かのアクションにつながることを期待します。
名前はベルタ。
一人の人生を大きく変えることのできる大きな存在でした。

最善の判断ができる力を
総務省管轄の行政監視行政相談センターから講師をお招きし、「行政とは何?」という基本的なところから、その在り方について学ぶ機会をいただきました。
本日の6校時。全学年を対象にした「避難訓練」が行われました。
常磐消防署から3名の消防士をお招きし、具体的な事例を基にした避難の際の注意点などを学ぶ機会をいただきました。
やはり、あの大震災を風化させてはなりません。
いずれにしても、その時、その場に応じて、最善の判断ができる力を子どもたち一人一人に身に付けさせなければならないと深く痛感いたしました。
そのような資質・能力を育んでいくために、子どもたちに付けたい力を様々な関係機関と共有し、そのための連携ができるような「社会に開かれた教育課程」の実現を今後も目指していきたいと考えております。


行き届く指導
そのため、テストのたびに見られる光景となりますが、廊下には教科書や参考書がぎっしり詰め込まれた背負いかばんがズラッと並ぶことになります。
その背負いかばんが整然と並んでいる姿からも、先生方の指導が入っていることが伺えます。
3年生のみなさん、お疲れさまでした。
今日で一区切りですが、また仕切り直しながら夢を叶えるための努力を継続していきます。
さて、いよいよ来週の水曜日。
今度は1、2年生のみなさんの学力テストが控えています。


まだまだ頑張れる
それでも、ちょっと目線を上げてみると、きりりと引き締まったような濃い青空が広がっていました。
2日後の月曜日、3年生は第5回学力テストを控えています。
現在志望している高校への受験に向けて、自分の背中を力強く後押ししてくれるような結果を得られることを願っています。
まだまだ頑張れることは、たくさん残されているはずです。

重なり合う
小編成を組んでのコンクール出場となりますので、音楽室の他に図書室やコンピュータ室などの空き教室を最大限に活用し、それぞれの“チーム”が音の重なり合い等を確認し合いながら練習に励んでいます。
どの“チーム”にもパートリーダーが存在し、的確な指示を出しておりました。
そこにはなにか、音だけではなく、また違う何かが重なり合っているようにも感じました。
アンサンブルコンクールいわき支部大会まで、あと1週間です。


学びのはじまり
そりゃぁ、これだけみんなが前のめりになるほど、夢中になりますよね。
だって、そこには修学旅行があるんですもん。
本日は、2年生の各教室で修学旅行班別自主研修の計画・立案をしているところにお邪魔しました。
「自分の行きたいところではなく、班として学びを深めることができる場所へ」
遊びではなく学びに行くのだということを大前提にした、合意形成を目指す話合い活動が行われていました。
ここにも普段の授業で培われた「主体的で対話的な学び」を垣間見ることができました。
修学旅行はもうすでに始まっています。


元気な笑顔があってこそ
遠い遠い昔の記憶をたどりたくなるような、なんともいえない郷愁に浸りたくなるような、そんな下校風景に出会うことができました。
本日は、職員会議のために、いつもより早い下校となりました。
学校では、この時期から来年度の教育課程実施に向けて、計画を練っていく段階に入ります。今年度の反省を生かし、さらに充実した教育活動を展開できるように立案してまいります。
まずはお子さんたちの元気な笑顔があってこそ。
そして、その笑顔に我々は救われているような気がします。


走り込んだ距離だけ
今日も息を弾ませながら走っている姿がありました。
本校では体育館で活動する部活動は、バスケットボール部、バレーボール部、卓球部の3競技のため、体育館を毎日使用することはできません。
体育館の割り当てになっていない日は、当然“外練”となります。
本日はバスケット部のみなさんが、その日でした。
走った距離は嘘をつきません。
走り込んだ距離だけ、一人一人の体力、走力となって、一人一人の自信につながるはずだと信じています。

残り4週間も地道な取組を
このような日々の地道な積み重ねが、大きな成果となって現れてくるのだろうなと感じます。
オレンジ色の朝日に照らされながら、一歩一歩を踏みしめながら走る姿には、なぜか心を打たれてしまいます。
さて、本日で三者教育相談が無事に終わりました。
大変ご多用の中、保護者のみなさまがご都合を付けていただき、学校まで足をお運びいただいたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。
2学期もいよいよ残すところ、あと4週間となりました。
もちろんこの4週間も、お子さん一人一人の充実した学校生活につながるような支援をしてまいります。


来週も欠席者が少ないことを願いつつ
この三者相談が終わりますと、3年生は県立Ⅰ期選抜の願書作成へと移ります。
もちろん私立高校においては、入学願書をすでに書き終えている高校もありますが、いよいよ現実味を帯びた進路事務が続いていきます。
1、2年生においては、学校や家庭での生活、学習への取り組みなど、三者教育相談を通して、何か一つでも、ちょっとした改善でもいいですので、目に見える変容があれば、大変うれしく思います。
本日は、欠席する生徒が非常に少ない一日となりました。
これも、保護者の方々のご家庭におけるご指導があってのこそです。
心より感謝申し上げます。
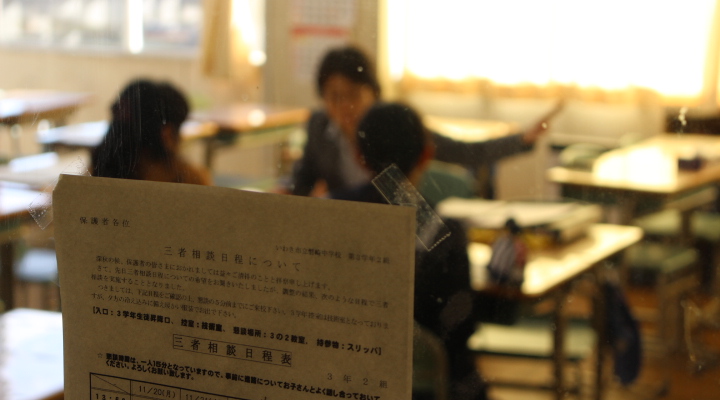
力強い朝日のように
写真ではうまく切り取ることができませんでしたが、なんとも言えない素敵な色合いでした。
さて、期末テストも終わったばかりですが、3年生は三者教育相談を通して現実を目の当たりにし、必死になって学習に取り組んでいることと思います。
先日もお伝えしましたように、3年生は12月4日(月)に学力テストが予定されています。その学力テストの結果が、現在の志望校受験への後押しとなるように、“今”を精一杯に頑張るしかありません。
今朝の素晴らしい朝日のように、力強い光を放ちながら進むべき進路に向けて着実に歩んでいくことを期待しております。

怪我に強い体 自分に負けない心
本日は日本トレーニング指導者協会から、スポーツトレーナーの永井隆太郎先生をお招きし、ウォーミングアップやストレッチの方法を具体的に学ぶ機会をいただきました。
1、2年生の運動部のみなさんが受講しましたが、ぜひ今回の学びを普段の練習等に生かしてもらえればと思います。
これからますます寒くなる中での練習だからこそ、体を温めるウォーミングは大切なはずです。
中体連で万全の状態で試合に臨むためには、怪我をしないための体づくりは重要なはずです。
そして、もちろん「自分に負けない強い心をツクル」ことも忘れません。


暖かい控え室をぜひご利用ください
そのような大変寒い中、学校まで足をお運びいただき、ありがとうございました。
保護者の方々と共有できました情報を基に、お子さん一人一人の充実した学校生活につなげていくようにしてまいります。
天気予報では、明日も気温がだいぶ低いようです。
保護者の方々の控え室を学年ごとに用意し、ストーブをたいて暖かくしておりますので、どうぞご利用ください。
3学年⇒技術室 2学年⇒家庭科室 1学年⇒第3会議室
(どの控え室も、お子さんの教室がある同じフロアにあります。)

保護者のみなさま、よろしくお願いいたします
本日は、ほぼすべての部活動が実施され、練習に励んでいます。
この一日、一日の練習の積み重ねがきっと春につながるはずです。
さて、いよいよ2日後の月曜日からは三者教育相談が1週間をかけて実施されます。
保護者のみなさまにおかれましては、ご多用の中、時間を割いていただきまして、ありがとうございます。
特に3年生にとりましては、今後の進路選択に向けた重要な面談になりますので、十分にお子さんと今後のことについて話し合いをした上で、三者教育相談に臨まれますよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。
もちろん、2年生、1年生におきましても、さらに充実した学校生活につながるような意義ある三者教育相談にしてまいりたいと考えております。
保護者のみなさま、何卒よろしくお願いいたします。


どれだけの準備をして、どれだけの気持ちで
それでも、本番の受験を考えた場合、3年生のみなさんにとっては、今回の期末テストの数十倍もの緊張感を持って試験に臨むことになるはずです。
期末テストを終えたばかりですが、来月4日(月)には、第5回学力テストが予定されています。
学力テストは、部活動でいう練習試合みたいなものです。
練習試合を通して自分の課題を見つけ、その課題の克服のために地道な練習を積み重ねていく。
みなさんが受験で合格するための“練習試合”も残すところ、あと3回となりました。
その“練習試合”に向けて、どれだけの準備をして臨み、どれだけの気持ちをもって臨むのか。
その臨む姿勢によって、結果が大きく変わってくるものと思っています。
さぁ、次の“練習試合”に向けた準備をいつから始めますか。

まだできる まだ頑張れる
静寂
前のめり
2学期期末テスト1日目。
どの教室からもなんとも言えない緊張感が伝わってきました。
さぁ、明日は2日目。
明日のために今やれることを精一杯に取り組みます。
今日の試験のときのような緊張感を持って明日の準備をします。
そして、明日も真剣・静寂・前のめりで頑張ります。

きれいに整然と
授業が終わった僕たちは、校庭に整然と並ぶ。
日ごろの指導が、にじみ出るような光景を目にすることができました。
まさしく生徒指導の機能を生かした授業の展開です。
さぁ、いよいよ明日から、2学期期末テストが始まります。
まだ残された時間はたくさんあるはず。
まだ残されたチャンスはいくらでもあるはず。
目標を達成するために、最後のひと踏ん張りに期待します。
ご家庭のみなさんからの最後の励ましを何卒よろしくお願いいたします。

足元を見つめる
上履きが一つも見当たらず、外履きのジャガーがきれいに並んでいることが欠席ゼロのサインです。
「はきものをそろえると心がそろう。
心がそろうとはきものもそろう。」
履物をしっかりと揃える。足元からしっかりを見つめる。
ご家庭での履物はどうなっているでしょうか。
学校での指導がご家庭でも実践されていれば、これまたうれしいことはありません。

信じたい、いや信じよう
先週からお伝えしてありますように、本日は我々教職員の研修のために、午前中での放課となりました。
どの生徒も一様に午前中で帰ることができることを喜び、満面の笑みをたたえながら下校する様子を目にしました。
「自宅に着いたらしっかりとテスト勉強をしてくれるのかなぁ」
そのような一抹の不安を抱かせるくらいの意気揚々とした表情でした。
その表情、これから精一杯にテスト勉強をがんばろうとする自信に満ち溢れた表情なんですよね...
きっと、頑張ってくれますよね...

地道な練習を乗り越えて
県新人大会を終えたばかりですが、来年度の春に向け、練習試合を通して課題を見つけ、そして、その克服に向けた地道な練習が続いていくのでしょう。
さて、プリントにて保護者のみなさまにはお知らせしてあるところですが、明後日の月曜日はお弁当のご準備をされなくて構いません。
お子さんの下校時刻は、11時40分となっていますので、自宅で昼食をとることができますよう、ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

本に恋する
そんな衝動に駆られることがよくあります。
もしかしたら磐崎中の生徒のみなさんも、期末テストの勉強から逃避して、ゆっくりと本を読みたいなと思っている人も少なくないかもしれません。
そこをぐっと我慢して、まずは期末テストに向けた勉強を精一杯やり遂げて、来週の金曜日の夜から読書に没頭してみてはどうですか。
きっと、図書室にいる恋人たちは、そっと静かに息を潜めて、みなさんが来てくれることを待っていてくれるはずです。

朝稽古
いよいよ今週末、剣道部が県新人大会の団体戦に出場してきます。
野球部と同様、もちろん剣道部も県大会での優勝を目指し、これまで鍛錬を積んできました。
ぜひ目標を達成できるよう、剣道部のみなさん、頑張ってきてください。
きっと、大丈夫です。
みなさんの後ろには黄金の防具を付けた「磐崎中 増田」がどっしりと構えていてくれるはずです。
その他に、特設部の柔道部とバドミントン部が個人戦に出場してきます。
試合に出場するみなさんの活躍を期待しております。

目的ではなく手段として
講師の先生、お二人をお迎えし、指文字で自己紹介をしたり、手話で「翼をください」を合唱したりと、手話を通して表現することを学びました。
もちろん、手話を学び、手話そのものを覚えることは大切ですが、でも、それ以上に大切なものがあるような気がします。
手話を介してコミュニケーションをとることにより、障害をもった方の思いを受け止めること。
手話を覚えることがゴールではなく、手話をツールとして、自分の世界を広げていってほしいと思います。
自分の手話はどのように見えているのか、その手話の向こうにいる人の存在が見えるものになってほしい、そう思いました。

立冬の輝き
そんな小春日和の一日でしたが、本日、2学年では県学力調査が実施されました。
本日までが「学校へ行こう週間」でしたが、昨日の高校説明会には90名を超える保護者の方々、そして高校説明会以外においても、この3日間の間、20名近くの保護者の方々に足を運んでいただきました。
わざわざ学校までお越しいただいたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。
さて、第2校舎の屋上に群生したすすきが、太陽に照らされて金色に輝いていました。
お子さんたちにも、来週に実施されます期末テストに向けて、本日のすすきのように輝きを放ちながら邁進していってほしいと願うばかりです。

高校進学のその先にあるもの
本日は、高校説明会が実施されました。
会場を3箇所に分け、いわき市内の9校の先生方にそれぞれの高等学校について具体的に説明をいただきました。
大変ご多用の中、9つの高等学校のうち、8つの高等学校では校長先生にわざわざ足を運んでいただきました。
先生方の話からは、「よりよい生徒を一人でも多く受け入れたい」という熱意が伝わってきました。
さて、受け入れていただく側の私たちにも、同じような熱意があったでしょうか。
当然のことですが、高校への合格、進学がゴールではありません。
高校進学後のその先にある未来が見える進路選択をしていきたいものです。本日も時間を調整していただき、多くの保護者の方々にお越しいただきました。
ありがとうございました。

粘り強く 根気強く
体育館からは、プレーをする選手たちの掛け声や応援団の大声援が聞こえてきます。
本校のバレーボール部は県大会への出場は叶いませんでしたが、今日は大会運営の補助員として役割を全うしています。
元気がよくて清々しいあいさつ、いつも小走りできびきびと動くバレー部のみなさんの姿は、本当に立派だなぁと感心してしまいます。
さて、野球部は昨日から相馬地区で開催されている県大会に出場しています。昨日と今日の試合で着実に駒を進め、明日予定されている準決勝まで勝ちあがったという報告を受けました。
これで県大会3位以上は確定しましたが、野球部は優勝しか見ていません。
先程、校地内を巡視していましたら、夏に紹介しました蝉の抜け殻が、まだ紫陽花の葉に残っていました。紫陽花はだいぶ色あせていましたが、それでも蝉の抜け殻は残っていました。
野球部のみなさんにも、蝉の抜け殻に負けないくらい、粘り強く、根気強く戦ってきてほしい。そう、願うばかりです。

学力の底上げをめざして
主体的に学習に取り組もうとする姿、積極的に対話し学びを深めていく姿、根拠を基に自分の考えを深めていこうとする姿、多くの教室でそのような姿を見ることができるよう、研究を進めてまいりましたが、一番の目標、それはただ一つです。
それは、目の前にいる生徒一人一人に確かな学力を身に付けさせること。
これからも、お子さんの学力向上を目指していくことはぶれずに、日々の充実した授業の展開を目指していきます。



我々大人も
もしかしたら我々大人は、情報モラルについて、子どもたちよりも本当の知識が不足しているのかもしれません。
もしかしたら我々大人は、情報モラルについて、わかっているつもりで本当の知識がないのかもしれません。
我々大人も、この子どもたちのような真剣な眼差しで、情報モラルというものに目を向けなければならないと思える機会をいただきました。
「学校へ行こう週間」の1日目。本日は情報モラル教室を実施いたしました。
時間に都合を付けてくださり、保護者の方々がわざわざ学校まで足を運んでくださることに感謝いたします。
ありがとうございました。

「正解」ではなく、「最適解」を
本日の「夢先生」は高橋 一馬先生。アイスホッケー競技の元日本代表選手として活躍されてきた方です。
やはり、どのような競技であれ、日本代表として世界に挑戦し、世界と戦ってきた経験を基にしたお話は、どの内容にも説得力がありました。
「正解は一つではない。方法はいくらでもある。」
高橋先生が伝えてくださった言葉ですが、これからの社会を生き抜いていかなければならない子どもたちにとって、大きな示唆を与えてくれるものだったはずです。
「与えられた正解ではなく、自分自身にとっての最適解を求めようとする力」
今、まさしく、この力を手に入れることが求められてくるはずです。


〒972-8317
いわき市常磐下湯長谷町家中跡28番地の5
TEL 0246-42-2978
FAX 0246-42-2957



