※本ホームページ内容について、無断掲載を禁止します。

※本ホームページ内容について、無断掲載を禁止します。
 いわき市立渡辺小学校
いわき市立渡辺小学校 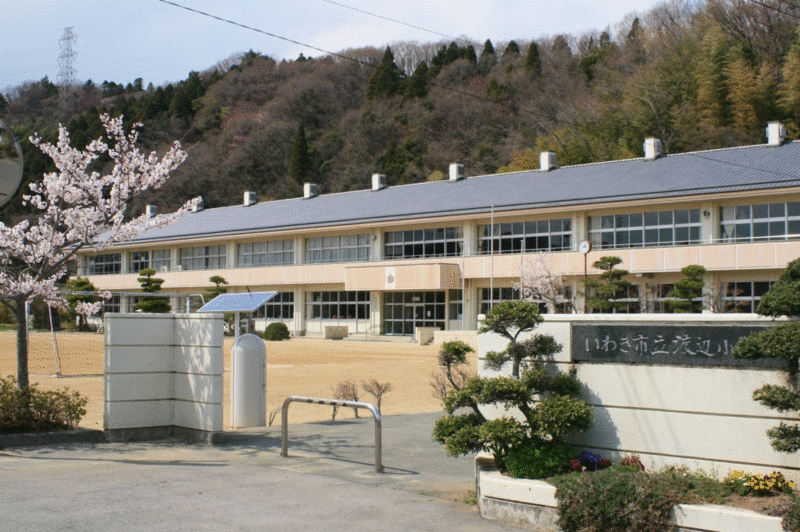
年末年始の時期、路面の凍結や帰省や旅行等による交通量の増加などにより、交通事故が多発する時期となります。
それを踏まえ、23日(月)に開催した服務倫理委員会全体会では、いわき警察署渡辺駐在所の鈴木様を講師にお招きし、交通事故の未然防止についてお話しいただきました。
飲酒運転、スリップ事故、速度超過など、いろいろ教えていただきましたが、その中でも特に印象に残った言葉が3つあります。
1つ目 3時間後の代行
忘年会や新年会など、年末年始は飲酒の機会が増え、代行を呼んでもすぐには来ないことがしばしばあります。
代行を呼んだものの、長らく待っている間に、待ちきれなくなってつい・・・とならないよう、3時間後のことを考えて、代行を呼びたい3時間前に予約しておくとよいというアドバイスです。
2つ目 リアウインドウも溶かしましょう
寒いこの時期、車の窓ガラスが凍ることがしばしば起きます。
フロントガラスやリアガラス、ドアミラーの凍結は溶かすものの、リアウインドウが見落とされがちなのだそうです。ところが、運転席から、リアウインドウ越しに視認しなければならない車左後方の情報はとても重要で、自転車や原付バイクの巻き込み事故もこれらの確認不足によるものが多いそうです。
3つ目 死角からの飛び出しに注意
対向車線が渋滞している時は要注意とのこと。その渋滞を横切りたい車がいた場合、その車が通れるよう譲ってあげた場合、譲られた車が勢いよく出てくることがあるそうです。「込んでて大変そうだな」ではなく、「車が隙間から出て来るかも」という「かもしれない運転」を心掛けてほしいそうです。
今回教えていただいたことをしっかり守り、渡辺小学校の教職員からは決して事故や違反が出ないよう、一人一人が心にしっかり刻み込みました。
ご多用の中、貴重な指導・助言をしてくださいました鈴木様ありがとうございました。
比較的暖かいいわきでも、今日はかなり冷え込んでいます。
早朝より教頭先生が体育館の暖房をつけて、少しでも温かい環境で第2学期終業式ができるよう準備してくれていました。感謝です。
「校長先生のお話」では以下の3点について話しました。
① 2学期、たくさんの行事などがあったが、みんな自分の目標をもって、真剣に、前向きに、あきらめずに取り組んでくれたことに、心から「ありがとう」と言いたいこと。
② 3学期は2学期以上に、やさしくて、あったかくて、いごこちのよい学校や学級となるような雰囲気をみんなの力でつくってほしいこと。
③ 冬休みには多くの人がいる所へ出かける機会もあることから、手洗い・うがいなどの感染予防対策をしっかり行って、元気に冬休みを過ごしてほしいこと。
児童作文発表では、1年、3年、5年の代表児童が2学期の反省と冬休みや3学期に頑張りたいことを発表しました。発表の概要は次の通りです。
〇 事例に綺麗に書くこと、お掃除、学習発表会の3つを頑張った。冬休みは宿題を速く終わらせて、お手伝いも頑 張る。
〇 走るのが苦手だったけど、体育のフットベースをきっかけに走るのがけっこう楽しいと初めて思った。これからも楽しく走りたい。冬休みになわ跳びを練習して、3学期に二重跳びを跳べるようになりたい。
〇 2学期は、校長先生の言う「寄り添う」ことがたくさんできていたと思うので、思いやりをもって過ごせたと思う。冬休みには、6年生からもらたアドバイスを生かして、心も6年生になる準備をしたい。
校歌は、これまでの式では、時間を考慮して1番だけ歌ってきました。しかし、卒業式も近づいてきたことも踏まえ、今日は久しぶりに3番まで歌いました。全員がしっかり歌えており、各学級で頑張って練習してきたことが目に浮かぶようでした。
式終了後、表彰伝達と、生徒指導の先生から冬休みの過ごし方について話を聞きました。
表彰伝達では、5名の児童に賞状や記念品を伝達しました。
「生徒指導の先生のお話」では、サッカーで使われる「レッド」「イエロー」「グリーン」の3枚のカードを示しながら、わかりやすく子ども達に話をしていました。
レッドは絶対にしてはいけないこと。命に関わること。
イエローは自分だけでやらないこと。例えば火を使うこと。
グリーンはぜひやってほしいこと。例えば規則正しい生活。
明日から15日間の冬休みです。
年越しして、2025年に変わります。
気持ちも新たに、新年を迎えられることを願っています。
皆様、よいお年をお迎えください。
本日、今年度2回目の避難訓練を実施しました。
今回は、地震発生から火災につながり、校庭へ避難するというものです。
いわき市小名浜消防署の方々にお越しいただき、子どもたちの避難の様子や、職員の通報の様子などを観察し、ご指導いただきました。ちなみに子どもたちの避難の様子は「良好」とのことでした。
前回は水消火器を使う体験をしましたが、マンネリ化してきているということで、担当が新たな試みを計画してくれました。それが消火栓を使っての消火活動です。
実際に学校に設置されているホースを使ってしまうといろいろ大変であることから、「常光サービス(株)」様のご協力により、学校に設置されているホースと同様のホースをお借りして消火訓練をしました。
当初の計画では、消防署の方に放水してもらう形で考えていましたが、消防署の方から、「ぜひ先生方でやってほしい」とのご提案をいただき、代表して教員2名が放水に係る仕事を体験しました。
ホースを持つ方を担当した教員によると、
「事前に放水の仕方を教えていただいていたから何とか出来たが、いきなり放水となったら、この水圧でうまくできなかったと思う。」
との反省が。やはり、実際に事前に経験できているというのは大きいですね。
子ども達も知っている先生が放水している様子を興味深げに見ていました。
その後、消防署の方からは、子どもたちの命を守る設備について教えていただきました。
① 防火扉が閉まっている時は、小さな扉を通って避難すること
② 消火器のある場所と使い方を覚えておくとよいこと
③ 非常口の看板は2種類あって、その違いを覚え、学校外でも安全に避難できるようにすること
最後に、代表児童3名が感想を発表しました。
「消火栓がすごかったです。」
「非常口の表示板が2種類あるのを初めて知りました。」
「消火器は10数秒使えることは知っていましたが、消火栓はずっと使えることが分かりました。」
「出かけた時には、非常口の表示板を探してみたいです。」等々
子ども達、事前に原稿を作ることなく、その場で考え、堂々と自分の気持ちを伝えていました。
しっかり学べているなあと感心しました。
今日の訓練を生かし、学校内でも学校外でも
「自分の命は自分で守る」
しっかり実行してくれることを願います。
毎週金曜日に実施している、一番人数の多い地区の登校班の子ども達との一緒の登校。
今日が2学期最後となります。
前回は出発してからの合流となってしまったため、いつもより早めに集合地点に行ってみました。
すると、すでに一人の子がお母さんと一緒に待っていました。
その後、続々と集まってきて、出発。
保護者の皆様や交通安全協会の皆様に見守られての道路横断。
学区内で一番交通量の多い道路の信号ですが、今回は素早く渡れて、赤になる前に渡り切ることができました。
運転手さんを待たせずに済んでよかったです。
その後は、班長さんを中心に、一列になって安全に登校できました。
もうすぐ多くの子ども達が楽しみにしているクリスマスです。
(ちなみに今日の給食の献立は「クリスマスメニュー」です。)
授業風景でもそれが感じられたので紹介します。
1年生が音楽科の時間に、クリスマスにちなんだ歌を歌っていました。
教室を覗いてみると、電子黒板に映し出された、数々のクリスマスにちなんだ歌の動画を見ながら歌っていました。
動画はアニメーションで、あわてんぼうのサンタクロースが煙突を覗いて落っこちるシーンなど、歌詞に関わる愉快な動きを見て、子ども達はニコニコしながら歌っていました。
楽しくて立ち上がったり、床に座り込んだりする子も見られるぐらい、子ども達は大盛り上がりでした。
音楽科や体育科など、いわゆる実技系の教科において、特に1・2年生で大切なことが「遊び」の要素です。
ただ知識や技能を教え込むのではなく、子ども達が楽しみながら、その教科の特性に触れて親しむようにすることです。
そういう視点では、今日の1年生の音楽科の授業はとても素敵なものだったと思います。
1年生の皆さん、ぜひおうちに帰ったら、おうちの人に歌って聞かせてあげてくださいね。
多くの学校の多くの学級で、この学期末に「お楽しみ会」的な活動が実施されます。
学級活動には大きく3つの活動内容があります。
(1)学級や学校における生活づくりへの参画
(2)日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
(3)一人一人のキャリア形成と自己実現
その中の「(1)学級や学校における生活づくりへの参画」として、子ども達が、なぜその会を開きたいのか、どんなことをしたいのか、役割分担はどうするのかなど、会を成り立たせるために必要なことを、担任の助言も受けながら、自分たちで話し合って積み上げていきます。
昨日18日は、2年生が、こうした積み上げの成果として「お楽しみ会」を開催しました。
黒板には、クリスマスをイメージした、とても素敵な絵や折り紙で作った飾りがつけられていました。
会を盛り上げようという強い思いが感じられます。
すべて子ども達が考え、準備したものだそうです。素晴らしい。
私がお邪魔したときには「くじ引き」と「フルーツバスケット」をやっていました。
くじ引きは全員が引き終わって、全員で一斉に開くタイミングでした。
一斉に歓声が上がり、すごい盛り上がりでした。
その様子を見たくじ引き担当の子ども達も、きっとうれしかったのではないでしょうか。
くじの景品も、時間をかけて丁寧に手作りされたものばかりで、頑張って準備したことがよくわかりました。
フルーツバスケットでは、みんなが楽しく活動できるよう、担任からの助言を受けながらなかよく活動していました。特に低学年では、楽しくなりテンションがあがってくると、ついつい、悪ふざけをしてしまったり、勝ち負けでもめてしまったりすることがあります。それらを想定し、事前に声かけをしていた担任はお見事でした。そのため、最後までもめることなく、楽しく活動ができていました。
「楽しむためにはルールを守る」
楽しい活動を通してしっかり学べていたようです。
冬休みに入る前に、こうしたイベントを経て、子ども達はまた一回り大きくなれたと思います。
昨日は、「性に関する指導」として、5・6年生を対象に、医療創生大学の池田先生を講師にお招きし「思春期の私たち」というテーマで授業を行いました。
今日は、3年生を対象に、性に関する指導を行いました。
テーマは「いのちのつながり」です。講師として、医療センターの助産師である佐藤先生にご来校いただきました。
最初に、助産師さんってどんなお仕事かを教えてもらいました。
日本では女性しかなれませんが、海外では男性の助産師さんもいるそうです。
続いて、お母さんのおなかの中で成長していく赤ちゃんについて学びました。
スライドに表示されるイラストを見ながら、へそのおの役割であったり、つめが伸びることが、赤ちゃんが順調に成長している証拠の一つであることなどを教えていただきました。
その後、「いのちの大切さ」について学びました。
「いのちはとってもたいせつ。
みんなのいのちは自分ひとりだけのものではない。
おなかの中で大切に育てられ、愛されて生まれてきた。」
佐藤先生のスライドの中で、特に印象に残る言葉でした。
最後に、本物の赤ちゃんと同じ大きさ、同じ重さの人形を抱いてみる体験や、先生が妊婦さんの大変さを疑似体験してみることをやりました。
人形ではあるものの、ほんものそっくりの赤ちゃんの人形をだっこする子どもたちの顔はみんな優しい表情でした。
担任の先生が妊婦さんになった時は大爆笑。
その後、妊婦さんの大変さを体験するため、妊婦さんになった状態で、床の物を取る体験をしました。
本当だと、なかなかとれなくて「妊婦さんて大変だよね」と話したいシーンだと思うのですが、担任の先生が苦労しているのをずっと見ていられない子ども達は、率先して床の物を取ってあげていました。本当に優しい子ども達です。
こうした経験を通して、一人一人がかけがえのないいのちをもっていること、十分に実感できたのではないでしょうか。
貴重な体験の機会を提供してくださった佐藤先生に心より感謝申し上げます。
地球温暖化やごみ問題、エネルギー問題など、我々はさまざまな環境問題を抱えています。
こうした問題にどう対処していて、これからはどうしていけばよいのか、子ども達が環境学習として学んでいきます。この環境学習は、国語科、社会科、理科、総合的な学習の時間などで取り組むことが多い内容ですが、6年生の図画工作科でも「環境学習」が取り入れられていました。
様々な環境問題を解決し、みんなが幸せに暮らせるにはどうすればよいか。
一人一人が自分の思いを込めて、工作として表現しました。
どれも、その子の趣味や特技、興味関心が高いことなどとの関連が図られており「なるほど、〇〇さんらしいな」と思う作品ばかりでした。
こうしたアイディアが、実際の科学の進歩につながっています。
6年生の素敵なアイディアの数々が、近い将来現実のものとなり、私たちの生活がより地球にやさしく、かつ豊かになっていくことを楽しみにしていたいと思います。
【周りの木が煙をきれいにしてくれる「エコ工場」】
【自分で発電する「自家製野球場】
【発電をする魚。黒いひもで発電の様子を再現しました。】
【魚が動けば発電される「魚の発電」】
【電気自動車のさらに上をいく「発電車」】
【地球温暖化を止める「地球アイス」】
【宇宙から地球を冷やして「地球温暖化を止めるエアコン」】
【落ち葉で発電する「落ち葉の学校」】
【「えんぴつ学校発電所」中の子ども達が鉛筆を動かすと発電します。】
【利用されなかった木材で建てられた「Eco cafe」】
【ゴミばこから電気を作る「ゴミ発電」】
【いいことをすると発電してくれる「クリスマスツリー」】
【ポイ捨て禁止!海の学校】
本校では、人間尊重、男女平等の精神に基づき自分や他者を尊重し、豊かな人間関係を築くことができる資質を育むこと、発達段階に応じて、性に関する問題に対して適切な意思決定や行動選択ができるようになることを目的に、全学年で性に関する指導を行っています。
本日は、医療創生大学の池田先生を講師にお招きし、5・6年生を対象に授業を行いました。
テーマは「思春期の私たち」思春期の心を体を知ること、互いに大切に・尊重できる関係づくりを学ぶことが本時の目標です。
まず、思春期の心の特徴について教えていただきました。
親から自立したい欲求がありつつ、親から離れる不安もある状況であったり、「自分らしさ」とは何かを探求し始める時期であったりすることなど、子ども達の中には、頷きながら聞いている子が多く見られました。
続いて、思春期の心の発達について学びました。
からだの発達に加え、大人になっていく「こころ」の発達についてもわかりやすく教えていただきました。
その他、MISP(マッサージ・イン・スクール・プログラム)の体験もしました。
MISPは、健全な人間関係の基礎であるケアと敬意に焦点を当て、子どもにとって安心できる安全な環境を作り出すツールとして考案されたものだそうです。
子ども達は、MISPの体験を通して、適切に人と触れ合うことよって生み出される安心感や一体感などを感じていたようです。
ご多用の中、子ども達に貴重な体験を提供してくださった池田先生、本当にありがとうございました。
(MISPの様子は、明日追加掲載する予定です。)
【(追加)MISPの様子です】
1年間の稲作体験の集大成として、本日、収穫祭を実施しました。
前日からの準備に加え、今日も朝早くから、いわき市青少年育成市民会議渡辺支部の皆様、田んぼの学校応援団の皆様、公民館の皆様、ご協力いただける保護者の皆様など、本当に多くの方々が準備をしてくださいました。
開会式では、この活動の中心となって支えてくださった、いわき市青少年育成市民会議渡辺支部長様より、
「感謝の心を持つこと」
「楽しんで行うこと」
などのお話をいただきました。
その後、いよいよ餅つきです。
最初はうまく臼の中央に杵を当てられず、周辺を叩いてしまう子もいましたが、だんだん慣れてきて、上手につけるようになっていきました。
その後は、自分の分のおもちをあんこやきなこと合わせて、あんこもち、きなこもちを作っていきました。
それと同時に、家庭科室ではお雑煮の準備も進めていただいていました。
他の学年の分のおもちは、事前に地域の皆様が作って準備してくださいました。
全員分のお餅が完成した所で、5年生が各学年へお餅を配って歩きました。
嬉しくて駆け寄ってくる低学年の子ども達、とてもかわいらしかったです。
閉会式では、これまで支えていただいたお礼として、5年生がリコーダーと鍵盤ハーモニカによる演奏を披露しました。
そして、お待ちかねのお昼の時間です。
今日は全校生がお弁当日なので、お餅をメインに食べている子が多かったようです。
子ども達だけでなく、私たち教職員もいっしょに、お餅を美味しくおなか一杯いただきました。
今年は特別に、「田んぼの学校応援団」の皆様が環境大臣賞を授業されたことを記念して、「祝」の文字が入ったお持ち帰り用のおもちも特別に用意してくださいました。
本当に何から何まで至れり尽くせりの「収穫祭」でした。
これこそ「渡辺ならでは」の体験活動だと思います。
貴重な体験を1年間支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。
こんな素敵な活動が、これからも末永く続けられることを切に願います。
〒972-8334
いわき市渡辺町田部字岸17番地の1
TEL 0246-96-6042
FAX 0246-96-6096