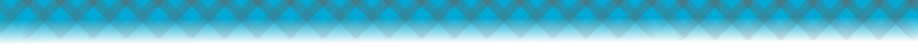
豊間中学校 Toyoma Junior High School

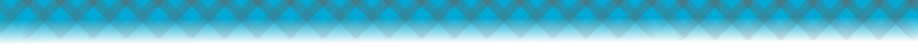
塩屋埼灯台点灯120周年記念式典が行われました。
本校からはお祝いの寄せ書きを作成した1年生を代表して5名の生徒がお祝いのメッセージを
また、2年生の鈴木皇成君が市英語弁論大会で優勝した英語でのスピーチを披露しました。
塩屋埼灯台点灯120周年おめでとうございます。
この節目の年にすばらしい式典に参加させていただき、とても貴重な経験となりました。
また、細かなご配慮をしていただいた海上保安部のみなさま、
本当にありがとうございました。
5,6校時は、1,2年生対象に、夢先生として「新井 周 さん」をお迎えして、「スポーツこころのプロジェクト 笑顔の教室」です。新井さん(以後、生徒たちの呼び方 周さん )は、北京出身の卓球選手で、6歳から卓球を始め、16歳の来日後も努力を重ね、アテネオリンピック日本代表や世界選手権でも活躍し、引退後は後進の指導・育成にあたっています。
第1部は、周さんとスタッフの生方さんのリードで体育館での活動です。まず、周さんと卓球のラリー。オリンピック選手はすごいです。次に,ゲーム形式のエクササイズ。考えながら身体を動かすことが大事ですね。第2部は、周さんからオリンピックに出場するまでの努力と夢にかける気持ちや考え方などのお話を聞きました。夢の実現に向けて3つのこと、①「夢があるのは幸せなこと」②「夢があるから頑張れる、我慢できる」③「夢をかなえるには感謝の気持ちを忘れないこと」は、あらゆる場面でとても参考になることだと思います。生徒たちが夢を探し、実現に向けて歩んでいくことで、人としてのパワーが身についていくと思います。とても貴重な時間でした。
1,2年生が福島県水産海洋センターと福島県海上保安部を訪問して、お話を聞いたり実際に体験したりしました。水産海洋センターでは魚の放射線調査などの様子を見たり、実際に調査船「いわき丸」に乗船して説明を聞いたりしました。お弁当の後は三崎公園でちょっとリラックスタイム。いい表情です。午後は海上保安部で仕事の内容や災害時の対応、負傷者の搬送などを学習しました。私たちの生活はたくさんの方々の力で守られていることや働く意義など様々なことを学習したと思います。所員の方からは、「生徒たちから海に携わる人がでてくるとうれしいなあ...」とのことでした。
FMいわきのBETTYさんのリードで、生徒とともに創り上げる講演会にしていただきました。「やってみよう①」では、早口言葉を練習して話し方のコツを学びました。ポイントの一つは「ちょうどいい声」ですよね。「やってみよう②」は「久一」の遠藤さんにも参加していただいてポーポー焼きつくりの実践ビデオ「ななちゃん'sキッチン」(彰太先生&奈那先生出演)を題材にしたディスカッション。BETTYさんのコーディネートでパネラーも生徒たちも思ったことを話すことができたと思います。BETTYさんのフリートークでは、生徒からの質問をネタに話し方・伝え方だけではなく、自分の考え方や職業や人間関係などにも関わるお話をしていただきました。最後の まなみさん からの生徒代表お礼の言葉は、講演から学んだことをしっかりと表現した立派なスピーチでした。さっそくの成果かな?
※以下BETTYさんのお話から、いくつかランダムにキーワードのようなものをあげてみます。なかなか深い・・・
1「声は人なり」 2話し方・伝え方のコツは「ちょうどいい声」「話す内容(伝えたいことは?)」「話す態度(これ大事)」 3目を見て話す、苦しいときは目を閉じて「うん...」と肯定 4緊張しても知っていることなら大丈夫(知っているというレベルまで練習する)、緊張する人は自分が好きな人 5本番前には練習する(当然だけど)、その前には「機嫌良くする(と一日がうまくいく)」 6自分を磨く時間は必要 7イライラする,うまくいかない、きれそう,には、自分の基準をつくる(この程度できれるのはダサいね) 8困ったときに助けてくれるのが親友ではなく、困っていたら助けたい人が親友 9信頼されるのがコミュニケーションの第一歩(信頼されるは相手が決めること、自分はただただ実直に続けていく)
1年国語、2年社会、3年数学の授業風景。文章を読む、書く、まとめる、解く、自分で考えることにじっくりと取り組んでいる時間です。授業では考えるためのパーツを集めて確認し、どのように組み立てるか工具としての手法、何をつくってどのように役立てるかという製品をつくるビジョンを学びます。何はともあれ、まず自分で考えることです。
〒970-0223
いわき市平薄磯字南作62
TEL 0246-39-4840
FAX 0246-39-4841